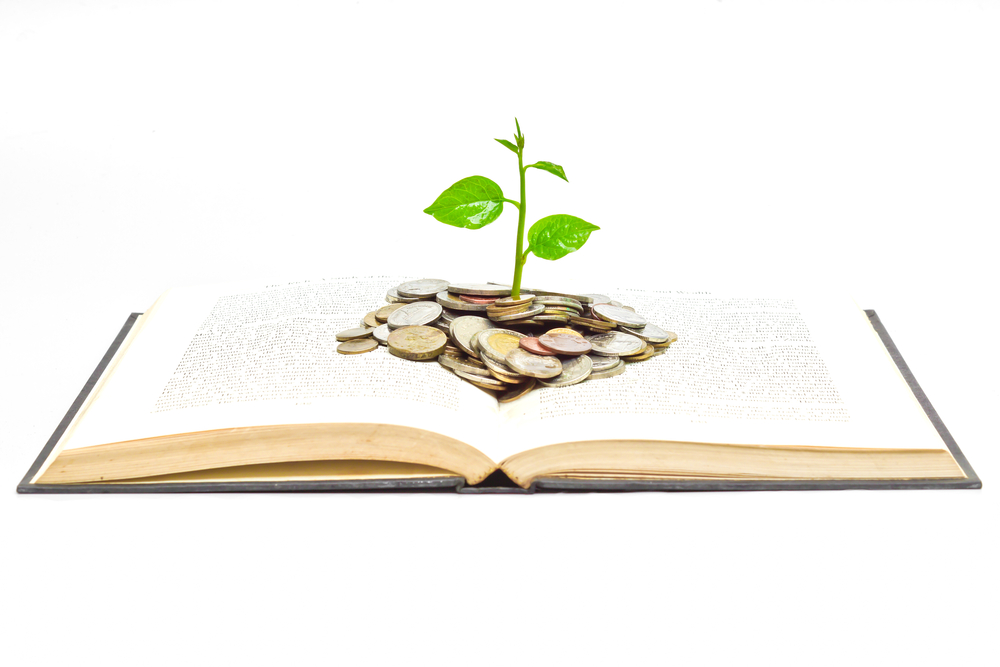今回は、教育資金の一括贈与について、確認していきます。
1 制度の目的
日本において、個人の金融資産を一番、多く所有しているのは60代になっています。
全体の個人金融資産の中に占める割合が、60代以上で6割になっています。
また、60代の1人あたりの平均的な金融資産の金額は、1,600万円以上になっています。
これに対して、子育て世代である30代の平均的な金融資産の金額は、30代で400万円、40代では700万円となっていますが、この世代は、住宅ローンを抱えており、住宅ローンが、金融資産の金額を上回っており、実質はマイナスの状況です。
この子育て世代の教育資金対策として、平成25年に『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』という制度が創られました。
2 制度概要
『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』は、平成25年4月1日から平成31年3月31日まで適用される制度です。
この6年間の間に直系尊属である贈与者が、子や孫名義の金融機関の口座に、教育資金を一括贈与した場合、子や孫の一人に対して、1,500万円までを非課税とする制度です。
3 現行の贈与の取り扱い
現行の相続税法の規定では、その都度、生活費用や教育費用について、親から子、祖父や祖母から孫に資金が贈与された場合、贈与税は、非課税となります。
これに対して、一括で生活費用や教育費用を贈与した場合、贈与税が、課税されます。
例えば、1,500万円を親から子に生活費用として、一括で贈与した場合、(1,500万円−110万円(基礎控除))×50%−225万円=470万円が贈与税として、課税されます。
これを『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』を適用すると、贈与税が非課税になります。
3 制度の対象となる教育資金とポイント
『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』の教育資金は、学校等に直接支払われるものが対象です。
学校等に直接支払われるものとは、学校の入学金、授業料、入学試験の検定料、保育園の保育料などが対象となります。
学校等以外のもの支払われるものでも、1,500万円までの非課税枠の中で、500万円までが、非課税枠として、認められています。
学校等以外もの支払われるものとは、学習塾、そろばん教室、習字教室などが対象となります。
この制度のポイントは、教育資金の使い途は、金融機関が領収書をチェックし、書類を保管しているということです。
よって、贈与された子や孫は教育資金を支払った際に領収書を保管しておく必要があります。
また、この制度は、孫や子供が30歳に達するまでの日に口座が終了します。
よって、この口座に残高がある場合は、贈与税が課税されるので、注意が必要です。
4 制度のメリットとデメリット
この制度のメリットは、孫や子供が30歳に達するまでに1,500万円の枠の中で、資金を使いきれば、贈与税が課税されないことです。
最近、高齢者の認知症が問題化されています。
しかし、この制度を利用すれば、祖父母からの贈与の場合、健康なうちに一括で贈与がしやすくなります。
この制度のデメリットは、金融機関が領収書をチェックするので、領収書の保管が必要なことです。
また、老後の資金からの捻出なので、贈与することにより、老後資金が、目減りしてしまうことと、
受贈者1人あたり1,500万円という制度なので、子や孫に公平に贈与することが、難しいことがあります。
この教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』は、相続税対策としては、有効な制度です。
この制度が出来たことにより、信託銀行の贈与税対策の口座開設が激増してきました。
この制度のデメリットにも注意して、制度の趣旨を理解して、60代で相続税対策をしようという方は、この制度の利用を検討されてください。