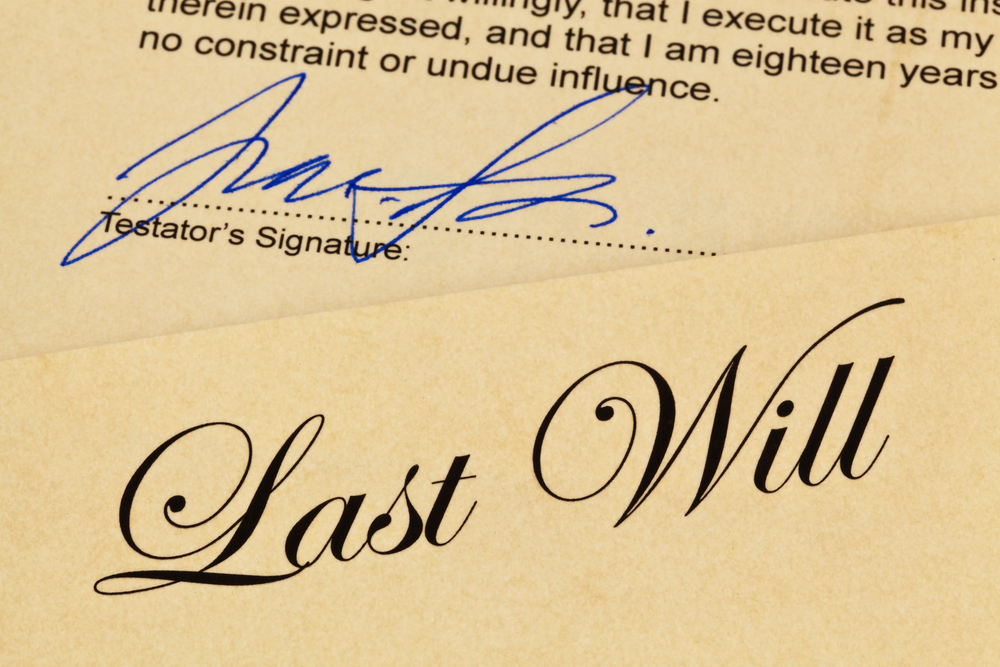今回は、相続対策の生命保険の活用と相続が発生した後に必要な手続きについて、確認していきます。
1 生命保険の死亡保険金の非課税限度額
死亡保険金には、相続税非課税限度額という枠があります。
被相続人が死亡したことによって取得する生命保険金のうち、被相続人が毎月の保険料を負担していれば、「500万円×法定相続人の数」の金額は、相続税は非課税となります。
よって、この枠を活用することで、相続税対策となります。
2 一時払い終身保険の活用
一時払い終身保険とは、保険料を最初に全額支払う終身の死亡保険です。
一時払い終身保険は、健康診断なし、または、年齢もかなり高齢でも加入できる商品もあります。
一時払い終身保険は、相続税対策として、効果を発揮します。
ただし、加入してから死亡までの期間が長引くと、資金の運用上、損失を招くことにもありえます。
よって、一時払い終身保険の加入時期は、よく検討するべきといえます。
1,000万円の預金を持ってる場合、そのままの金額が、相続税の評価額とされます。
法定相続人が2人の場合、1,000万円で「一時払い終身保険」に加入します。
これにより、1,000万円相続財産が、相続税が非課税の財産とすることができます。
よって、使う見込みのない預金を持っているよりか、「一時払い終身保険」への加入をしたほうが相続税対策になるわけです。
3 預貯金の凍結解除
亡くなった方の名義の預貯金は、銀行で引き出せなくなる可能性があります。
銀行などの金融機関は、預貯金口座の名義人の死亡届などで名義人が死亡したことを知った場合、その名義人の預貯金口座を凍結するからです。
預貯金口座が凍結されると、口座からお金が引き出せません。
また、公共料金などの自動引落も止まります。
よって、この預貯金の凍結を解除する必要があります。
相続は、金融機関に対し、亡くなった方の名義の預貯金以外に、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書の提出が必要になります。
これにより、金融機関は、相続人が特定でき、口座に引き継ぎ人の立場が把握できるので、亡くなった方の預貯金の凍結が解除されます。
よって、生前の時に預貯金の管理をどうするかを、被相続人と相続人どうしでよく話し合っておくべきです。
4 葬祭費や埋葬料支給の手続きについて
亡くなった方が国民健康保険の加入者の場合、喪主に対して葬祭費が支給されます。
亡くなった方が健康保険の加入者本人の場合、埋葬料として、健康保険で扶養されている方が死亡した場合でも、家族埋葬料として、5万円が支給されます。
埋葬料の受給手続きは勤務先が行ってくれるので、勤務先であった会社に確認しましょう。
葬祭料と埋葬料ともに、請求の期限は死亡した日から2年になります。
よって、期限内に忘れずに請求しましょう。
5 住宅ローンの手続について
住宅ローン契約時には、団体信用生命保険に加入しなければなりません。
亡くなった方の名義で住宅ローンが残っていた場合でも、団体信用生命保険が適用されて、住宅ローンは終了します。
よって、遺族の方が住宅ローンを引き続き支払う必要はなく、遺族のかたが住んでも問題ないです。
住宅ローンが残っている場合は、借入をしている銀行に連絡して、銀行に死亡の報告を行うと、住宅ローンの担保として、建物と土地に設定されていた抵当権抹消のための書類が渡されます。
この書類をもとに、抵当権の抹消手続きを行います。
今年から相続税が税制改正となり、相続税対策のセミナーが賑わっており、書店には、相続税対策の本が多く並んでいます。
相続対策の生保の活用と相続発生後の手続きについて、今から準備しておくべきでしょう。